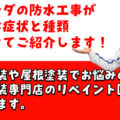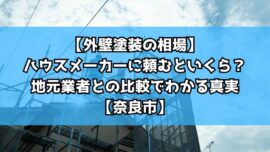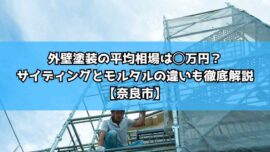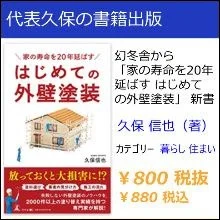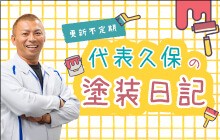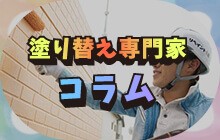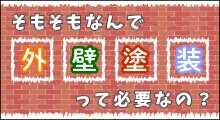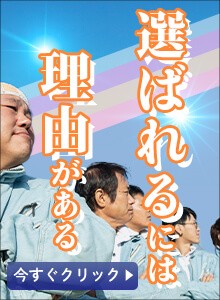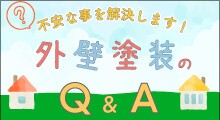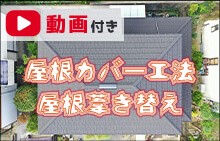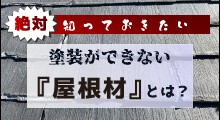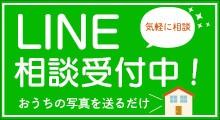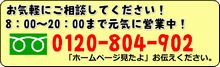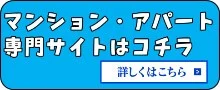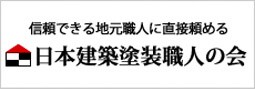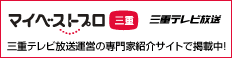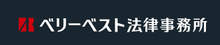高圧洗浄(外壁).jpeg)
外壁の直貼り工法と通気工法の違い〜外壁塗装しても耐久年数が変わる理由…奈良市の塗装業者が徹底解説【▶解説動画あり】
リペイント匠の久保です。
今回は「外壁塗装における直貼り工法と通気工法の違い」について解説します。
外壁塗装は、住宅の外観を美しく保つだけでなく、建物そのものの寿命を延ばす重要な工事です。しかし、実際に塗装を行う際には、工法の違いによってその耐久性や効果が大きく異なることをご存じでしょうか?外壁の劣化や雨漏りの原因は、単なる塗装の問題ではなく、外壁の構造自体が影響していることも多いのです。
特に「直貼り工法」と「通気工法」は、外壁の湿気管理や通気性に大きく関わる要素であり、どちらの工法が採用されているかによって、塗装の持ちや劣化のリスクが異なります。もし、外壁にひび割れや浮きが見られたり、塗装が剥がれたりしている場合、単なる塗り替えだけでなく、工法自体に注意を払う必要があるかもしれません。
この記事では、これらの工法の違いをわかりやすく説明し、どちらが自分の家に適しているのか、どのようにメンテナンスすべきかについて、具体的なアドバイスを提供いたします。
この記事を参考に、今後の外壁塗装の際に失敗しないための判断材料にしていただければ幸いです。
目次
直貼り工法と通気工法の基礎知識

直貼り工法と通気工法の2つの工法には、それぞれの特性と利点・欠点があります。これらを理解することで、外壁塗装の効果を最大限に引き出し、長期間維持できるかどうかが大きく変わってきます。
直貼り工法とは、下地の構造用合板に直接サイディングを貼る方法です。この工法は、1980年代から2000年頃まで主流でしたが、通気性がないため湿気が内部に溜まりやすく、経年劣化によって外壁材の裏側が腐食するリスクがあります。
一方で、通気工法は、胴縁(どうぶち)を使って外壁材と下地の間に空気の層を作り、湿気を外に逃がす仕組みです。この工法は、湿気が内部に溜まるのを防ぎ、外壁の耐久性を高める効果があります。
直貼り工法と通気工法の特徴とメリット・デメリット
直貼り工法が普及した理由は、施工の簡便さとコストの低さにあります。当時は通気性に対する認識が浅く、建物の湿気管理についてもあまり考慮されていませんでした。
しかし、住宅の耐久性が問題視されるようになると、通気工法の優位性が注目され、2000年代以降は通気工法が標準化されました。
直貼り工法の特徴とデメリット
直貼り工法は、かつて多くの住宅で採用されていたものの、現在ではさまざまなデメリットが問題視されています。特に外壁の耐久性や湿気の管理に関する課題が顕著であり、現代の住宅工法と比較すると多くのリスクを抱えています。
①通気性がないため湿気がこもりやすい
直貼り工法の最大のデメリットは、通気性が確保されないことです。外壁と下地の間に隙間がないため、湿気が逃げ場を失い、外壁内部にこもりやすくなります。特に梅雨や湿度の高い季節には、湿気がたまりやすく、下地材やサイディングが腐食する原因となります。結果として、外壁全体の耐久性が低下し、建物自体の寿命を縮めるリスクが高まります。
②経年劣化による外壁の剥がれや浮き
直貼り工法では、サイディングを直接下地に固定しているため、経年劣化とともに外壁が剥がれたり浮いたりする現象が起こりやすくなります。特に湿気の影響で下地材が劣化すると、外壁材がしっかり固定されず、剥離や浮きが発生します。この状態を放置すると、外観の悪化だけでなく、塗装も剥がれやすくなり、外壁全体がさらに劣化します。
③内部の腐食が進行しやすい
湿気がこもることで、外壁の内側で見えない部分に腐食が進行することがあります。直貼り工法では、外壁の下に空気の流れがないため、湿った状態が続きやすく、これがカビや腐食の原因となります。特に、内部で腐食が進むと、外から見ただけでは問題を確認できず、問題が深刻化してから発覚することが多いです。
④改修やメンテナンスが難しい
直貼り工法は、外壁材と下地が密接に貼り付けられているため、外壁内部の問題を発見することが難しくなります。湿気や腐食が進行しても、外から確認するのは困難で、問題が深刻になってから修繕を行うと、修繕範囲が広がりコストが大幅に増加するリスクがあります。直貼り工法を採用している住宅は、定期的にしっかりとしたメンテナンスが求められますが、それでも経年劣化を防ぐのは難しい点がデメリットです。
⑤塗装が持続しにくい
直貼り工法の住宅は、塗装を行っても再び剥がれやすいという課題があります。湿気がこもりやすいため、塗膜がしっかりと定着しにくく、数年経過すると再塗装が必要になるケースが多く見られます。これは、外壁の基盤自体に問題があるため、塗装だけでは根本的な解決が難しいという点が、この工法の大きな弱点と言えます。
通気工法の特徴とメリット
通気工法は、直貼り工法の欠点を補う形で進化し、現在では外壁塗装における標準的な工法として広く採用されています。特に湿気対策や外壁の耐久性向上に優れており、建物の寿命を大幅に延ばすことが期待できます。
①湿気を外に逃がす構造
通気工法の最大の特徴は、外壁と下地の間に通気層を設けている点です。この通気層が、湿気や水分を建物内部にこもらせず、効率的に外に逃がす役割を果たします。これにより、外壁や下地材が常に乾燥状態を保つことができ、腐食やカビの発生を防ぎます。特に、雨が多い地域や湿度の高い気候で、この工法は大きな効果を発揮します。
②外壁の耐久性向上
湿気を排出できることで、外壁材や下地材が長期間にわたり良好な状態を保つことができます。直貼り工法と比べると、通気工法で施工された外壁は、耐久性が格段に向上し、劣化しにくいという利点があります。これにより、外壁の塗装が剥がれるリスクも減少し、メンテナンスの頻度も低く抑えられます。結果的に、建物全体の寿命を延ばすことが可能です。
③外壁の温度を均一に保つ 通気工法は、外壁と下地の間に空気の流れを作り出すため、外壁の温度を均一に保つ効果があります。夏場は外壁が過度に熱くなるのを防ぎ、冬場は外壁が冷えすぎるのを抑えることで、建物内部の温度管理にも役立ちます。これにより、建物全体の断熱性能が向上し、室内の快適性が高まります。
④地震や振動にも強い
通気工法では、胴縁を使ってサイディングを固定するため、外壁全体がしっかりと固定されます。これにより、地震や振動が発生した際に外壁が剥がれにくく、構造的な強度が向上します。特に、長期間にわたって安定した外壁を保ちたい場合、この工法が有効です。
⑤メンテナンスが簡単
通気工法では、外壁材が下地から離れているため、メンテナンスが比較的簡単に行えます。例えば、外壁に一部劣化や損傷が見られても、通気層があるために他の部分への影響が少なく、部分的な修繕や補修がしやすいのです。これにより、長期的なメンテナンスコストを抑えることができます。
⑥結露を防ぐ効果
通気層によって空気が流れるため、外壁内部で結露が発生しにくくなります。結露は外壁や下地に湿気を与え、腐食やカビの原因となるため、それを防ぐ効果がある通気工法は、住宅の健康を保つうえで非常に有効です。結露対策は、特に寒冷地での建物にとって重要なポイントです。
直貼り工法と通気工法のチェック方法とお客様へのアドバイス
お客様自身で外壁の状態をチェックする際、重要なのは「水切り」と呼ばれる部分です。これはサイディングの下部に取り付けられた金属製の部材で、雨水が内部に侵入するのを防ぐ役割を果たします。
水切り部分の簡単なチェック方法
まず、水切り部分に定規やものさしを差し込んで、隙間の深さを確認しましょう。2センチ以内しか入らない場合、直貼り工法の可能性が高いです。これに対して、3センチ以上入る場合は、通気工法である可能性が高くなります。このように、簡単な工具を使って外壁の状態をチェックすることができます。
通気工法のチェックポイント
通気工法の場合、サイディングと下地の間に隙間があり、この隙間によって湿気が逃げていきます。外壁にカビや腐食の兆候がないか、また塗装が剥がれていないかも合わせて確認することが重要です。
直貼り工法のリスクと注意点

直貼り工法の場合、塗装をしてもすぐに剥がれる可能性があります。特に、湿気が原因で外壁が劣化している場合、再塗装を行っても同じ問題が繰り返されることが多いです。
そのため、直貼り工法であれば、場合によっては外壁材そのものの張り替えを検討する必要があります。
塗装によるメンテナンスの限界
外壁の塗装は、建物の見た目を美しく保ち、外壁を保護するために重要な役割を果たします。しかし、特に直貼り工法の外壁においては、塗装だけでは根本的な問題を解決できない場合があります。
外壁塗装を行うと、外壁表面に新しい塗膜が形成され、外観が美しくなるだけでなく、外壁材が紫外線や風雨から守られます。塗膜ができることで、直貼り工法の外壁でも一定期間は水分の侵入を防ぎ、外壁材を保護することができます。特に、塗装の初期段階では、ひび割れや外壁の傷みが目立たなくなり、建物全体が新築のように見えることがあります。
しかし、直貼り工法の外壁では、サイディングと下地の間に通気層がないため、湿気が内部にこもりやすくなります。この湿気が長期間たまることで、下地材やサイディングの裏側が腐食しやすくなります。塗装を施しても、この内部の湿気問題が解決されるわけではありません。
塗膜は外からの水分を防ぐ役割を果たしますが、外壁の内側から発生する湿気や結露には対応できません。結果として、塗装が剥がれる原因となることや、外壁材そのものが内部から劣化してしまう可能性が高いです。特に、直貼り工法ではこうした問題が起こりやすく、見た目はきれいになっても、数年後には再び塗装の剥がれや劣化が発生するケースが少なくありません。
通常、外壁塗装の耐用年数は10年から15年程度とされていますが、直貼り工法の外壁では湿気の影響を受けやすいため、塗装の持続効果が短くなる可能性があります。湿気が内部にこもることで、塗膜が剥がれやすくなり、塗装を行ってから数年で劣化が進行することがあります。
これは、塗装の仕上がり自体には問題がなくても、外壁の構造上の問題によって塗膜の劣化が早まるためです。塗装の剥がれや膨れが発生すると、再塗装を余儀なくされ、頻繁にメンテナンスが必要になるため、結果的に費用がかさむことになります。
外壁の張り替えが必要な場合の判断基準
外壁の塗装を何度も繰り返しても劣化が進行する場合や、外壁材自体が損傷している場合には、塗装では解決できず、外壁の張り替えが必要になることがあります。
特に、サイディング材が大きく浮いている、あるいは割れが進んでいる場合は、張り替えが必要なタイミングです。これは、外壁内部の湿気や腐食が進行している可能性が高く、外壁材そのものの機能が失われています。
外壁の張り替え工法では、建物全体の外壁材を一新するため、根本的な修繕を行うことができます。張り替え工法は、劣化した外壁材をすべて撤去し、新しい外壁材を取り付けることで、建物の耐久性を大幅に向上させます。これにより、建物の寿命を延ばし、湿気や腐食、カビといった問題も根本から解決できます。新しい外壁材は最新の技術を用いて製造されているため、断熱性や耐火性、防音性も向上する場合があります。
ただし、外壁の張り替えは、塗装に比べて大規模な工事となるため、費用が高くなる点がデメリットです。張り替え工事では、古い外壁材の撤去費用や新しい材料費、人件費がかかるため、数百万円単位の予算が必要になることが多いです。そのため、工事を行う前にしっかりと見積もりを取り、予算を確認することが重要です。
専門業者による点検と適切なアドバイス

外壁塗装の状態や工法を正確に把握するためには、専門業者による定期的な点検が必要です。業者は、お客様の住まいの状況に応じた適切なアドバイスや、最適な塗装工法を提案してくれます。
業者選びのポイント
信頼できる業者を選ぶためには、過去の施工実績や口コミを確認することが重要です。また、施工後のアフターフォローや保証が充実しているかどうかも判断材料となります。塗装業者がしっかりと説明を行い、施工内容に納得できるかどうかを確認することも大切です。
無料点検サービスの利用方法
多くの業者では、無料の外壁点検サービスを提供しています。このサービスを利用することで、現状の外壁の状態を把握し、必要な修繕やメンテナンスを計画的に進めることができます。遠慮せずに問い合わせてみましょう。
まとめ
今回の記事では、外壁塗装における「直貼り工法」と「通気工法」の違いについて解説しました。また、外壁の状態をお客様自身でチェックする方法や、塗装の耐久性を高めるための具体的なアドバイスもお伝えしました。
外壁は家の美観だけでなく、建物全体の耐久性にも大きく関わる重要な要素です。直貼り工法や通気工法の違いを理解し、適切なメンテナンスを行うことで、長期間にわたり快適な住環境を保つことができます。
外壁塗装や屋根塗装に関する疑問や質問などございましたら、お気軽に、0120-804-902(8:00〜20:00)まで「ホームページ見ました」とお問合せしてください。
奈良県奈良市を中心に、お客様に最適なアドバイスを提供いたします。
外壁塗装や屋根塗装、防水工事でお悩みの方はお気軽にお問合せしてください。
詳しくは、奈良市のショールームの情報をご覧ください。
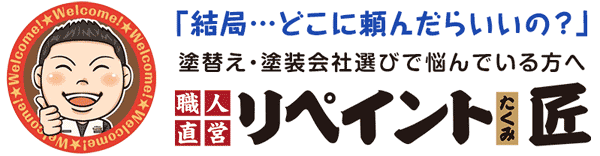



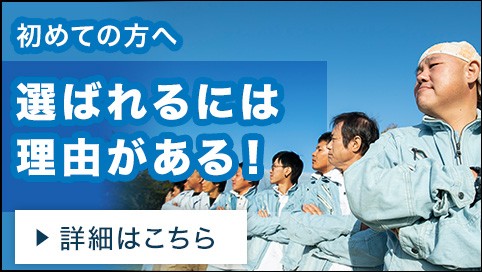

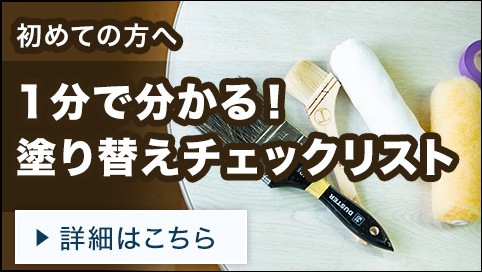
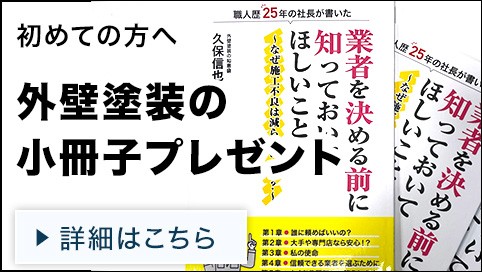


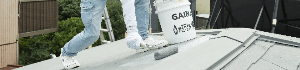



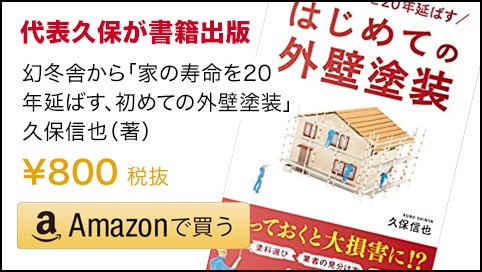

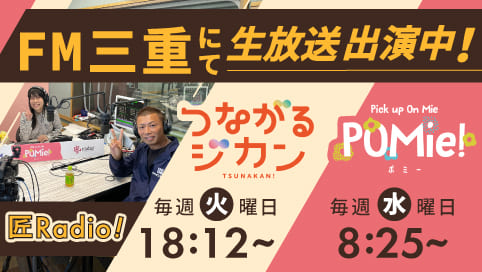
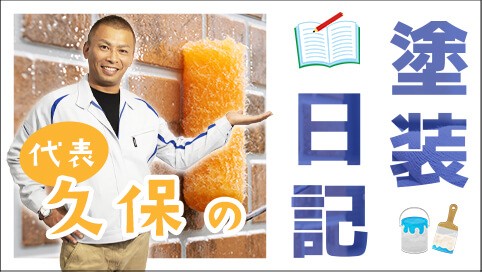




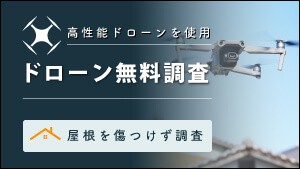
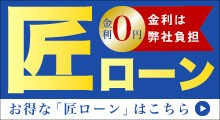
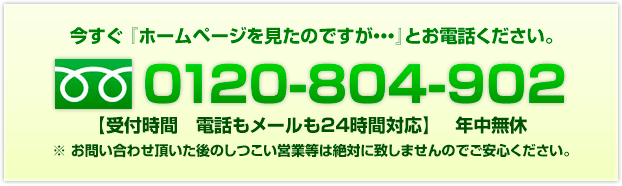
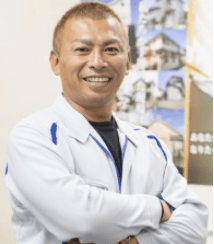
軒天(上塗り)-120x120.jpeg)
-120x120.jpeg)