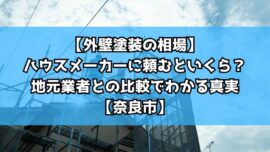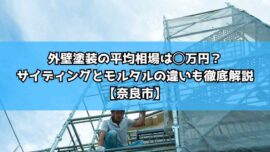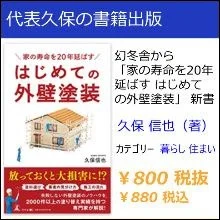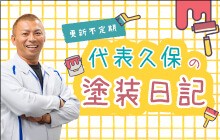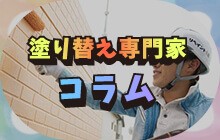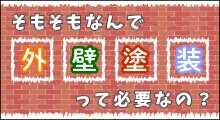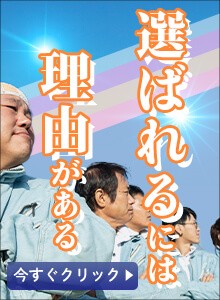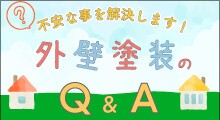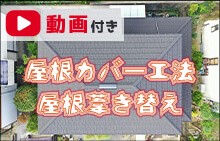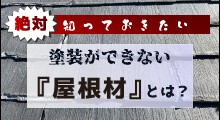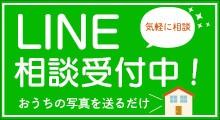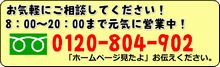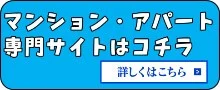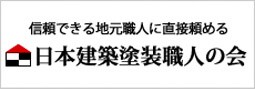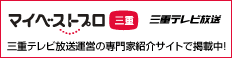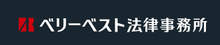屋根(上塗り1)-1.webp)
外壁塗装で塗料の使用缶数を見積書に明記するのが難しい理由!奈良市の塗装業者が徹底解説
こんにちは!リペイント匠の久保です。
外壁塗装の見積もりを依頼する際、お客様からよく「塗料の使用缶数を見積書に明記してほしい」といったご要望をいただきます。
一見すると、使用する塗料の量を事前に把握することで、安心して施工を依頼できると考えるのは当然のことです。結論を申しますと、実際の外壁塗装では、塗料の正確な缶数を見積書に明記することは難しいという現実があります。
本記事では、外壁塗装の見積書に塗料の使用缶数を明記することが難しい理由を、具体例を交えてわかりやすく、奈良市のリペイント匠が解説します。また、初回塗装と再塗装における違いや、色による塗り回数の変動など、実際の施工現場で起こるリアルな状況についても詳しくお伝えします。
外壁塗装を検討している方が、見積もりや施工内容に納得し、安心して依頼できる一助となれば幸いです。
目次
外壁塗装で塗料の使用缶数を明記するのが難しい理由
外壁塗装において、塗料の使用缶数を見積書に明記するのが難しい主な理由は、現場ごとの条件や塗料の特性によって使用量が大きく変わるためです。見積もりを正確にするためには多くの要素を考慮する必要があり、事前に使用缶数を確定させることは現実的ではありません。
ここでは、その理由を「外壁材の違い」と「塗料の種類と施工方法」の2つの観点から詳しく見ていきましょう。
外壁材や表面の状態による吸い込みの違い
外壁材にはさまざまな種類があり、その材質や表面の状態によって塗料の吸い込み具合が大きく異なります。以下の要素が塗料の使用量に影響を与えます。
①外壁材の種類
外壁にはサイディング、モルタル、スタッコ、リシンなど多くの種類があります。例えば、以下のような特徴があります。
- サイディング:比較的平滑で吸い込みが少ない。
- リシン仕上げ:表面が粗く、塗料を多く吸い込む。
②表面の状態
古い外壁やダメージがある外壁は、塗料をより多く吸い込む傾向があります。特に、初回の塗り替えでは吸い込みが激しくなるため、予想以上に塗料を消費することがあります。
③塗布面積とカタログの目安
塗料のカタログには「1缶あたり○○平米塗れる」と記載されていますが、これはあくまで理論値です。実際の現場では、壁の材質や吸い込み具合によって大きな誤差が生じます。
例:モルタル壁の塗装では、下塗りの段階で塗料が予想以上に吸い込まれ、追加の塗料が必要になるケースがよくあります。
施工方法による違い
施工方法も、塗料の使用量に大きく影響します。
外壁塗装は通常、下塗り・中塗り・上塗りの3回塗りが基本です。しかし、次のような状況がよく見られます。
- 下地の状態によっては下塗りを追加する必要がある。
- 塗料の色や仕上がりによって塗り回数が増えることもある。
例えば、外壁の傷みが激しい場合、下塗りで塗料を多く消費してしまうことがあります。また、塗装途中で追加の調整が必要になることもあり、事前に缶数を正確に予測するのは難しいのです。
初回塗装と再塗装で必要な塗料の量は違う
外壁塗装の塗料使用量は、初回塗装と再塗装では大きく異なります。初めての塗装の場合、外壁が塗料を吸い込みやすくなるため、予想以上に塗料が必要になることがよくあります。一方、2回目以降の塗り替えでは、既存の塗膜がしっかりと形成されているため、塗料の吸い込みが抑えられ、使用量が少なくて済むのです。
初回塗装は塗料の吸い込みが多い
外壁塗装の初回施工では、外壁材が塗料を大きく吸い込んでしまうため、塗料の量が増加します。特に、モルタルやリシン仕上げの壁は表面が粗く、多くの塗料を必要とする傾向にあります。さらに、経年劣化によって外壁材の表面が傷んでいる場合、その影響はさらに顕著です。
例えば、長年メンテナンスが行われていない外壁では、下塗りの段階で塗料が予想以上に吸い込まれます。通常であれば1回の下塗りで済むところが、吸い込みが激しいために追加で塗料を使わざるを得なくなるのです。
また、吸い込みを抑えるために塗装を重ねると、塗料の缶数も増加します。これは施工業者にとっても想定外のことがあり、見積書に事前に正確な量を明記するのが難しい要因のひとつです。
再塗装は塗料の使用量が抑えられる
一方、2回目以降の塗り替えでは、すでに前回の塗膜が形成されているため、塗料の吸い込みは抑えられます。塗膜が壁面を覆っていることで、下地が塗料を過剰に吸い込むことがないためです。
ただし、再塗装の場合でも、塗料の種類や外壁材の状態によっては、塗料の使用量が変わることがあります。例えば、塗膜が劣化してひび割れや剥がれが発生している場合、その部分を補修し、塗料をしっかりと定着させる必要があります。また、前回の塗装色が濃い色だった場合、明るい色へ変更する際には追加で塗り重ねる必要もあるため、塗料の缶数が増えることも考えられます。
このように、初回塗装と再塗装では塗料の使用量が異なるものの、壁の状態や塗装色の違いによっても変動するため、正確な量を事前に明記するのは難しいのです。業者が見積書で予測する量はあくまで基準値に過ぎず、現場の状況に応じて柔軟に対応することが求められます。
塗料の色や仕上がりによる塗り回数の違い
塗料の色や仕上がりの美しさは、外壁塗装において重要な要素です。しかし、色や仕上がりの違いが、塗り回数や塗料の使用量に大きな影響を与えることはあまり知られていません。
仕上がりの美しさを追求すると、事前に塗料の使用量を正確に見積もることが難しくなるのです。
明るい色は塗り回数が増える
外壁塗装で明るい色や白色を選ぶと、塗り重ねが必要になります。その理由は、白や淡い色の塗料は透明度が高く、下地の色が透けやすいためです。例えば、既存の外壁が濃い茶色の場合、その上から白色を塗ると下地が透けてムラになりやすくなります。この状態を防ぐためには、複数回の塗装が必要です。
一般的に、白色の塗装では3回以上の塗り重ねが必要になることがあります。下塗りでしっかりとベースを整えたとしても、白色の塗料はカバー力が弱いため、均一な仕上がりを目指すには追加の作業が必要になるのです。このため、明るい色を選んだ場合は、塗料の使用量が増えることを理解しておく必要があります。
色の特性や塗料の調整方法
一方、濃い色や暗い色の場合、塗料のカバー力が高く、塗り回数は少なくて済むことが多いです。例えば、グレーやダークブラウンなどは下地の色が透けにくいため、2回塗りで十分な仕上がりが得られることがあります。しかし、濃い色の場合でも、施工の際に注意しなければならない点があります。それは、塗料の厚みや仕上がりの均一さです。
濃い色は塗りムラが目立ちにくい一方で、塗膜が均一でないと部分的に仕上がりが不自然になることがあります。この問題を防ぐために、塗装業者は塗料の希釈具合や塗り方を細かく調整しながら作業を進めます。
さらに、仕上がりの美しさを左右するのは塗料だけではありません。外壁の状態や下塗りの品質も大きく影響します。例えば、下地の処理が不十分だと、塗料がしっかりと定着せず、仕上がりが悪くなることがあります。そのため、塗装業者は塗り回数や塗料の調整を現場で柔軟に判断し、最適な仕上がりを追求するのです。
見積書に塗料使用量を明記しない理由とお客様への理解

塗料の使用缶数を見積書に明記しない理由については、これまで解説してきたようにさまざまな要因があります。しかし、業者側が明記を避ける本質的な理由は、外壁塗装の現場では予測が難しい変動要素が数多く存在するからです。お客様に納得していただくためには、こうした背景を理解していただくことが重要です。
予測が難しい現場状況
外壁塗装は、現場ごとに条件が異なります。塗装面の材質や劣化具合、塗料の種類、施工方法など、さまざまな要素が絡み合い、塗料の使用量が変わってくるのです。たとえば、同じ「25平米」の面積でも、外壁の素材がモルタルである場合とサイディングである場合では、塗料の吸い込み具合が異なるため、必要な量が大きく変わります。
また、塗装前の下地の状態も予測を難しくします。外壁にひび割れや剥がれがあれば、補修をしてから塗装を行いますが、その補修部分は通常よりも塗料を多く吸収します。さらに、塗装途中に予期しない吸い込みが発生することもあり、施工業者は現場で柔軟に調整をしなければなりません。
お客様に「塗料の缶数を正確に教えてほしい」と言われても、これらの現場の変動要素を完全に事前予測することは困難です。そのため、見積書には目安としての塗料使用量を記載することはあっても、具体的な缶数を明記することは現実的ではありません。
塗料余剰や不足によるトラブル回避
塗料の缶数を明記した場合、現場で塗料が余ったり不足したりすることで、施工業者とお客様の間にトラブルが発生する可能性があります。
たとえば、見積書に「塗料5缶使用」と記載していたとします。しかし、実際には外壁の吸い込みが激しく、6缶必要になった場合、追加分の塗料代を請求するのかどうかという問題が発生します。逆に、塗料が余った場合は「余った分を返金してほしい」とお客様が要望されることもあるでしょう。
しかし、塗料の使用量は現場の状況に応じて変わるものであり、施工業者が事前にすべてを把握することは不可能です。さらに、塗料は開封後の保管が難しく、余っても再利用ができないことがほとんどです。そのため、塗料の使用量に関する細かな対応がトラブルにつながらないよう、見積書には明確な缶数を記載せず、施工現場で柔軟に対応する方が現実的なのです。
お客様には「塗料の使用量は目安であり、現場の状況によって変動する」ということを事前に理解していただくことが重要です。施工業者としては、適正な量を使用し、ムダを最小限に抑える努力をしています。正確な仕上がりと品質を保つためにも、塗料使用量については現場判断が欠かせないという点をご理解いただければと思います。
まとめ~奈良市の外壁塗装・屋根塗装なら
外壁塗装の見積書に塗料の使用缶数を明記しない理由について解説してきました。
お客様にとって「塗料の量がはっきりしないのは不安」と感じることは理解できます。しかし、外壁塗装という工事の特性上、塗料の使用量は事前に正確に予測することが難しく、現場ごとに変動するものです。
今回の記事でお伝えした要因から、塗料の使用量は現場の状況や塗料の種類、色、塗装の工程によって大きく変動します。そのため、見積書に具体的な缶数を記載することは現実的ではなく、むしろトラブルの原因になりかねません。施工中に塗料が余ったり不足したりする場合、追加請求や返金といった問題が発生するため、業者はあらかじめ柔軟に対応できるようにしています。
お客様にご理解いただきたいのは、塗料の使用量を見積書に明記しないのは「施工業者の手抜き」や「不誠実な対応」ではないということです。むしろ、現場の状況に応じて最適な量の塗料を使い、品質の高い仕上がりを提供するための判断です。施工業者としては、ムダを最小限に抑えつつ、外壁塗装の耐久性と美観を最大限に高めることを最優先に考えています。
これから外壁塗装を検討する方には、現場のリアルな事情を理解し、見積もり内容をしっかりと確認することをおすすめします。塗料の量だけにこだわるのではなく、仕上がりの品質や施工後の耐久性を重視することで、満足度の高い外壁塗装が実現できるはずです。
リペイント匠では、診断から最適な塗装プランの提案までお手伝いいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。外壁塗装や屋根塗装に関する疑問や質問などございましたら、0120-804-902(8:00〜20:00)まで「ホームページ見ました」とお問合せしてください。
奈良県奈良市をはじめ、奈良市を中心に、お客様に最適なアドバイスを提供いたします。
外壁塗装や屋根塗装、防水工事でお悩みの方はお気軽にお問合せしてください。
詳しくは、奈良市のショールームの情報をご覧ください。
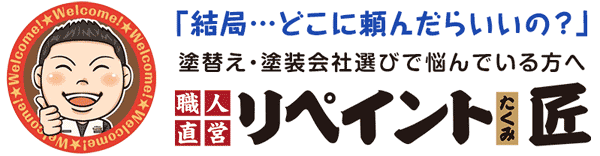



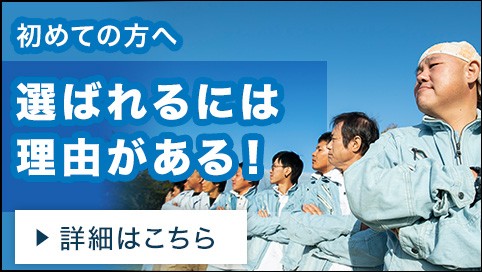

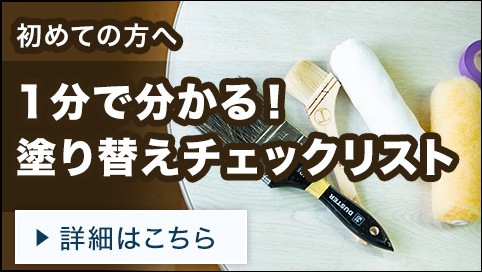
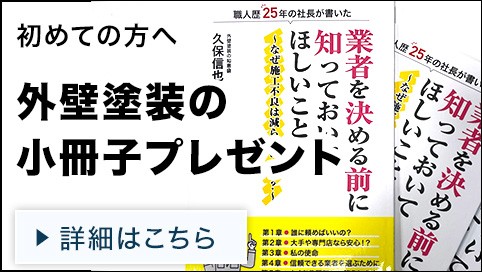


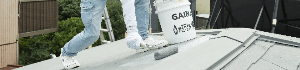



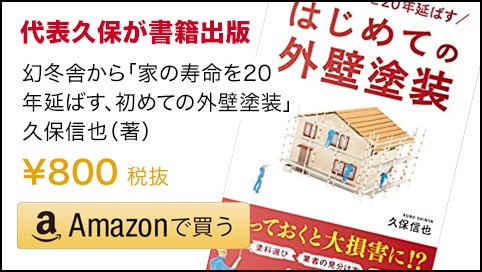

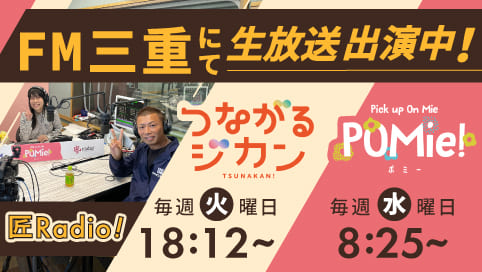
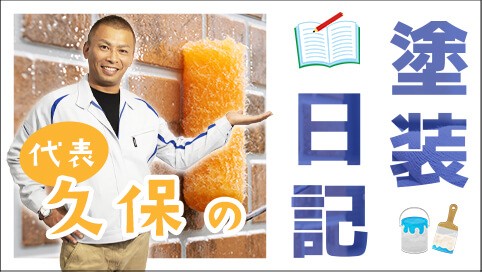




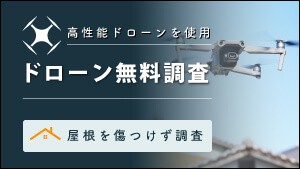
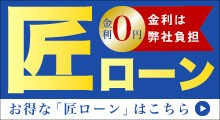
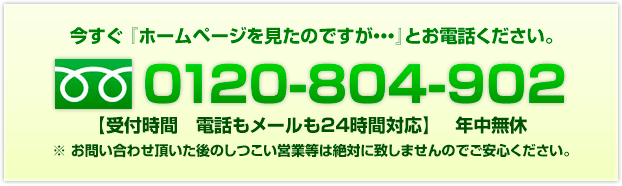
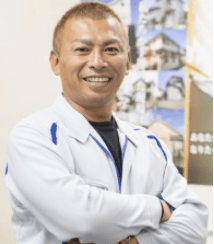
_塀(2回目)-120x120.jpeg)
_樋(1)-120x120.jpeg)